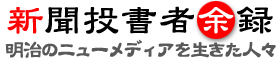投書者file.006:四屋純三郎
目次
略歴
四屋純三郎(よつや じゅんざぶろう)は、宮崎出身の慶應義塾教授。平民。1854(安政元)年~1884(明治17)年。15歳で福沢諭吉の慶應義塾に入塾し、その後、塾や交詢社においてさまざまな活動に携わったが、早世。
投書
四屋純三郎の投書は2件。1875年と1879年と間が空いているが、いずれも『郵便報知新聞』に掲載されている。
『郵便報知新聞』1875年11月18日
1875(明治8)年11月の投書は、「官員の給料過分なり減ぜざる可からざるの議」という表題が付されている。高すぎる官僚の給料を下げよ、というタイトルである。そして本文で、給料をなぜ下げる必要があるのか、その理由を論じている。
投書は一般論から始まる。
「凡そ天下の品物及び労力の價」は、「時と事情」によって、「自然」に「高低の差」が生まれる。しかし「自然」に反して価格に手を加えれば、どれほどの「弊害を醸生する」か、「實に測るべからざるなり」
では一国の政府はどうか。
「巨大の歳入金額を要し、強盛の権力を有する」政府は、「其力の大なるに乗じて物価高低の自然の道を妨碍し、大害を世に生出すること屢〔しばしば〕」である。
そして、この「大害」の「生出」は「我が国政府」も例外ではない。その実例が、官僚の給料である。
「今我が国政府の有様を見るに、亦此弊を免れざるものあるが如し。何ぞや役人の給料過分なる是なり」
ここからが本題である。なぜ「役人の給料」が高いことが問題なのか。役人の給料は人々の税金であり、そして役人も人々と同じ社会に属している以上、社会のルールに従うのは当然だからだ。
「役人の給料は何れより来たるや。先ず其出所を知らば、自ら其過分なるを悟らん。それ役人の給料は政府の歳入の中より供するものなり。而して其歳入なるものは、皆人民の膏血を絞りて取立てたる収税なり。……而して役人となる所の人物は我々社会中の人物なり。決して天より降り下りたる者に非ず。……我々社会中の金銭を以て、我々社会中の人に給与する、何ぞ社会中の法則に従て之を分与せざるべけんや」
四屋が述べる「社会中の法則」は、民間を基準とする。民間では、月の稼ぎは多くとも数十円どまりであるのに対し、中級以上の官員は数百円も受け取っている。官員の給料は民間の「法則」に反しており、官員は「不当の金」を得ているのだ。
四屋はさらに続ける。高給が一部の官員に限られるのであれば、問題はまだ小さい。しかし、人々が寛大にもこのような「役人の不当の罪」を許せば、社会に貧富の差が生じるのだ。それを「不問」にすることはできない。
「人民の至寛至大の心を以て、役人の不当の罪を恕するとするも、其不当は決して役人のみに止らず、廣く世に延蔓して大害を引き興し、遂に恕すべからざるの甚しきに至る……其弊一般に廣がりて、天下の人種に貧と富との別を生ずるが如きに至りては、何ぞ之を不問に措くべけんや」
しかも、官員の給料が民間に比べて非常に高いことは、「更に甚しき無形の大害」を生み出す。民間において志をもって勉学し成功したとしても、月の稼ぎがわずか数十円にしかならないのであれば、人々は数百円を容易に得られる官員になることを目指すようになってしまう。それが何をもたらすか。
「世に増殖せしものは、紛々たる腰抜の生ま書生のみ」
という有様になるのだ。
そして最後に次のように議論をまとめる。
「以上の所論にて役人の給料は過分にして大不当なるに決し、随て大弊害を世に引起すの具となること明なり。……徳義上……経済上……智学上より考ふるも均しく是れ大害の源なり。……三重の災難を免るるの道を求めること、今日に於て最も緊要なる處置と考ふるなり。諸君以て如何とす。
在野の慶應義塾教員らしい投書である。
『郵便報知新聞』1879年4月28日
さて2件目の投書が掲載された1879(明治12)年は、国会開設運動が全国に拡大した年。翌年、「国会期成同盟」が設立される。
「病後の感」と題された投書は、国会開設の必要性を、人間の病気を素材に述べたエッセイ風の投書である。
人間は、「病体漸く復して病苦僅に去るや、再び不養生の覆轍を踏まんと」する。つまり、喉元過ぎれば熱さを忘れ、同じ失敗を繰り返す。そしてこれは社会でも同じである。
「天下方〔まさ〕に治まりて稍〔や〕や安を愉むを得るや、驕奢の念乍〔たちま〕ち生じ、親〔みずか〕ら弊害を除きたるの手を以て、又弊害を作らんとす」
社会がこのような「不養生の覆轍」を踏まないためにも、国会が必要なのだ。
「人民に参政の権を許與して、治者の驕奢を戒め、……以て変乱を未然に防ぐの国会を設立する」ことが、「治世の妙案」である。
ところで、なぜ病気をたとえに用いたのか。理由が最後の一文で述べられている。自らが病気になった経験から、この投書を考えついたのだった。
「予今春病に罹り、名医の力に藉て幸いに治するを得たれども、更に病根を一掃せんと欲し来りて、熱海の温泉に浴す。偶〔たまた〕ま感ずる所あり、聊か録して以て自ら戒め且世に質す」
自身の病は治癒したと述べているが、熱海に静養しているところをみると、おそらく完治はしなかったのだろう。四屋はこの投書の5年後、1884(明治17)年、わずか30歳(数えで31歳)の若さで世を去ることになる。
参考資料
『明治過去帳』
四屋純三郎の項には、次のように記述されている。
「慶應義塾教授 日向延岡の人にして安政元年生まる。明治12年交詢社設立後、編緝事務を擔当し、本朝政体の著あり。17年12月20日肺患を以て郷里に歿す。年31。(時事新報)
「幕末・明治初期雑誌目次集覧」
論文のタイトルのとおり、雑誌の目次が収録されており、雑誌に掲載された邦訳論文の訳者として、四屋純三郎の名が記載されている。
※所蔵:「国立国会図書館デジタルコレクション(藤元直樹,2006,「幕末・明治初期雑誌目次集覧」『参考書誌研究』65)」
『福沢諭吉門下 人物書誌大系30』
四屋が慶應義塾に入塾したのは、1869(明治2)年6月26日、15歳のころであった。その後慶應義塾の教員となり、「英文講学」を担当したとされている。
※出典:丸山信編,1995,『福沢諭吉門下 人物書誌大系30』日外アソシエーツ
『都市民権派の形成』
澤大洋『都市民権派の形成』によれば、四屋は「三田演説会」において、1875年~1877年にわたり、たびたび演説を行なっている(54~55ページ)。
※出典:澤大洋,1998,『都市民権派の形成』吉川弘文館
『本朝政體』(1880年)
四屋編集の書籍。奥付に、「鹿児島県平民」と記載がある。この時期は、宮崎県は鹿児島県に含まれていた。
※所蔵:「国立国会図書館デジタルコレクション(四屋純三郎編『本朝政体』)」
投書一覧
- 『郵便報知新聞』1875(明治8)年11月18日
「官員の給料過分なり減ぜざる可からざるの議」 - 『郵便報知新聞』1879(明治12)年4月28日
「病後の感」